「電動自転車は楽じゃない?」という疑問を持つ方々へ。
電動自転車の普及が進む中、その利便性や快適さが注目される一方で、実際の使用感や運用上の課題についての声も少なくありません。
本記事では、電動自転車の真の特性や、普通の自転車やロードバイクとの違い、そして「電動自転車は本当に楽じゃないのか?」という疑問に迫ります。
電動自転車の持つアシスト機能の魅力、その一方での課題や注意点、そして適切な選択と使用方法について、詳しく解説していきます。
この記事を読むことで理解できる内容は以下の通りです
- 電動自転車が「楽じゃない」と感じる主な理由
- 電動自転車のアシスト機能の限界と速度制限
- 普通の自転車やロードバイクとの違い
- バッテリーのメモリー効果とその対策
電動自転車が「楽じゃない」と言われる理由とは?

電動自転車は近年、多くの人々にとって欠かせない移動手段となっています。
その理由は、アシスト機能による楽なペダリングや、坂道でもスムーズな走行が可能であるためです。
しかし、一方で「電動自転車は楽じゃない」と言われることがあります。
その理由としては主に以下の4つが考えられます。
電動自転車は楽じゃないと言われる理由
- 普通の自転車より重い
- 充電が面倒くさい
- 盗まれないよう気を使う
- 段差は苦手
電動自転車は普通の自転車より重い

電動自転車はそのアシスト機能を持つためのモーターやバッテリーの存在により、その重量が増加するのは避けられません。
実際に、多くの電動自転車は26kgから35kgの範囲での重さがあります。
これは、例えば一般的なロードバイクが7kg〜8kg、クロスバイクが10kg前後、普通の自転車が20kg前後であることを考えると、電動自転車の重さはかなりのものです。
この重さの主な要因は、バッテリーと電動アシストシステムです。特に、大容量のバッテリーは数キロの重さがあるため、その影響は無視できません。
このような重さがあるため、日常の使用シーンでの取り回しや駐輪時には、その重さを強く感じることがあります。
特に、女性や高齢者にとっては、この重さは日常的な使用においても負担となる可能性があります。
しかし、この重さがある一方で、アシスト機能のおかげで坂道などの走行時には非常に楽な走行を実現しています。
そのため、使用シーンや目的に応じて、電動自転車のメリットとデメリットを理解し、適切に選択することが重要です。
電動自転車は充電が面倒くさい

電動自転車の利便性と快適さの裏には、バッテリーの存在が欠かせません。
しかし、このバッテリーの充電作業は、一部のユーザーにとっては日常の一部として捉えられる一方、他のユーザーからは煩わしいものとして感じられることがあります。
特に、毎日の使用を前提とする都市部のコミューターなどは、日常的な充電作業に手間を感じることが少なくありません。
具体的には、バッテリーの取り外しや、専用の充電器を使用する必要があるため、充電場所の確保や、充電器の保管場所の確保など、細かな手間が積み重なることが挙げられます。
一般的な電動自転車のバッテリーは、フル充電に3〜6時間程度を要するため、急な外出や予定変更に柔軟に対応することが難しくなることも考えられます。
外出先や目的地での充電を考えると、専用の充電設備やコンセントの確保が必要となります。
これは、長時間の外出や旅行を計画する際には特に考慮すべきポイントとなります。
電動自転車を盗まれないよう気を使う

電動自転車の普及とともに、その盗難件数も増加の一途をたどっています。
特に、高性能なモデルやブランド品は、盗難のターゲットとして狙われやすい傾向にあります。
都市部を中心に、電動自転車の盗難事件は多く、ユーザー自身が防犯対策を怠るわけにはいきません。
実際のところ、多くの電動自転車ユーザーは、駐輪時には二重ロックを施す、夜間は室内に保管するなど、基本的な対策を取っています。
しかし、これだけでは十分ではない場合もあります。
例えば、盗難の多いエリアや、見知らぬ場所での長時間の駐輪は避ける、GPSトラッカーを取り付けるなどの対策も考えられます。
電動自転車の価格帯が高くなるにつれ、盗難保険の加入はほぼ必須と言えるでしょう。
万が一の盗難時にも、保険の適用を受けることで、経済的なダメージを最小限に抑えることが可能です。
盗難リスクを下げるための具体的な方法や最新の防犯技術についても定期的に情報を更新し、自身の対策を見直すことが大切です。
坂道は得意でも段差は苦手

電動自転車は、アシスト機能のおかげで坂道をスムーズに登ることが得意です。
一方、多くの電動自転車はタイヤのサイズが小さいモデルが主流となっており、この小さなタイヤが段差の乗り越えにおいて不利となります。
タイヤが小さいと、段差に対する衝撃を直接受けやすく、また、持ち上げる際の力も増えてしまいます。
歩道の段差など、日常生活で頻繁に遭遇する小さな段差でも、電動自転車の重量を感じながら乗り越える必要があります。
このため、電動自転車を選ぶ際には、使用する場所やルートの特性を考慮し、段差の多いエリアでの使用を予定している場合は、タイヤの大きさやサスペンションの有無など、乗り心地に関するスペックを重視することがおすすめです。
電動自転車は「楽じゃない」わけはない?違いと特性をよく知ろう
電動自転車は楽じゃないという意見があるのは確かですが、その機能をちゃんと生かせば楽じゃないわけはありません。
電動自転車と普通の自転車とロードバイクとの違い
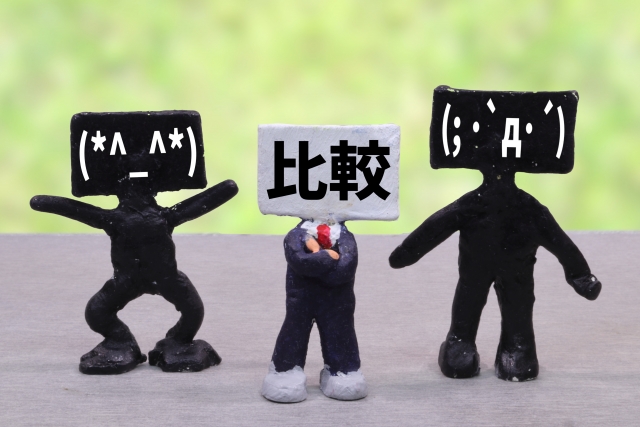
電動自転車、普通の自転車、そしてロードバイク。これら3つの自転車タイプは、それぞれ異なる特性や用途に応じた設計がなされています。
電動自転車の最大の特徴は、バッテリーとモーターによるアシスト機能です。
この機能のおかげで、坂道や向かい風の中でも、ライダーの脚力を大幅にサポートしてくれます。
具体的な数字で言うと、アシストを活用することで、ライダーは平均で約40%のエネルギー消費を削減できると言われています。
一方、普通の自転車は、エンジンやバッテリーを搭載していないため、全体的に軽量で、日常の短距離移動や運動を目的としたサイクリングに適しています。
そして、ロードバイクは、高速での走行を目的とした設計が特徴です。
細いタイヤとエアロダイナミクスを追求したフレーム形状により、風の抵抗を最小限に抑えることができます。
しかし、アシスト機能は持たず、ライダーの脚力のみで駆動するため、トレーニングや競技を目的とした使用が主となります。
また、ロードバイクはこの中で最も軽量であるため、ちょっとした移動や持ち運びであれば、電動自転車より楽だと感じるシーンも多いでしょう。
電動自転車は遅い?:速度に関する誤解
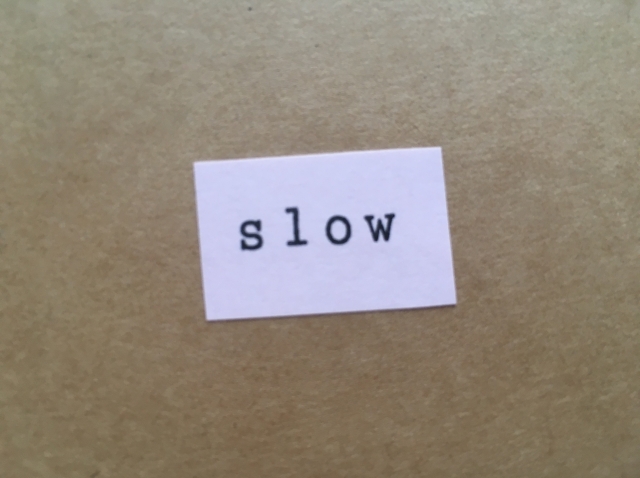
電動自転車は、アシスト機能を持つことで、坂道や風の強い日でもスムーズな走行をサポートしてくれます。
しかし、一般的な認識として「電動自転車は速い」と思われがちですが、その目的は「速さ」ではありません。
電動自転車のアシスト機能は、時速24kmを超えると自動的にオフになります。
これは、安全性を確保するための規定に基づいています。
つまり、電動自転車は、速く走るためのものではなく、ライダーのペダリングをサポートし、快適な走行を提供するためのものと言えます。
時速24kmより速いスピードが出せないわけではありませんが、アシスト機能がなくなるため、車体が重い分、普通の自転車よりもスピードが出しにくいと思うかもしれません。
一方で、速く走ることを目的とする場合、ロードバイクのような専用の自転車が適しています。ロードバイクは、軽量でエアロダイナミクスを追求した設計により、高速走行を実現します。
電動自転車 リミッター 解除 代行サービス

電動自転車の性能を最大限に引き出したいというユーザーの間で、リミッター解除代行サービスの利用が増加しています。
その背景には最高速度の向上を求める声が多いことが示されています。
この代行サービスを利用することで、専用の機器や技術を持つプロフェッショナルが安全かつ確実にリミッターを解除することが可能となります。
しかし、リミッターを解除した電動自転車の公道での走行は日本の法律「道路交通法」で禁じられているため、その使用は特定の場所や状況に限定されなければなりません。
代行サービスだけでなく、電動自転車のリミッターをカットするキットなどがネットで堂々と売られているのも見かけますが、これを利用してリミッターをはずし、公道を走ることは法律違反となるため、決してしてはいけません。
電動自転車のアシスト力の理解
電動自転車のアシスト力は、ペダリングの力をセンサーが検知し、それに基づいてモーターが補助するシステムによって動作します。
具体的には、ペダルを踏む強さが10Nの場合、アシスト比率が200%の設定であれば、モーターから20Nの補助力が加わり、合計30Nの力で走行することができます。
このアシスト力の特性を理解することで、坂道や風の強い日などの厳しい環境下でも、疲れにくく、効率的な走行を実現することができます。
また、アシスト力の調整機能を活用することで、バッテリーの持ちを良くしたり、運動効果を高めることも可能です。
したがって、日常の走行状況や体調に応じて、アシスト力を適切に調整することが、長距離の快適な走行やバッテリーの効率的な使用に繋がります。
バッテリーの容量と走行距離の関係

電動自転車の性能を左右する要因の一つが、バッテリーの容量です。
具体的には、バッテリー容量が400Whの場合、平均的な使用条件下で約60km〜80kmの走行が可能とされています。
この数値は、アシストの強度や走行環境、ライダーの体重などによって変動します。
一方、容量が600Whの高容量バッテリーを搭載したモデルでは、約90km〜120kmの走行が期待できると言われています。
しかし、バッテリー容量の増加は約2kg〜3kgの重量増となるため、取り扱いや持ち運びの際の負担も考慮する必要があります。
したがって、日常の使用範囲や目的に合わせて、最適なバッテリー容量を選択することが求められます。
メモリー効果とバッテリーの寿命

電動自転車のバッテリー、特にニッケル系のバッテリーに見られる「メモリー効果」とは、部分的な充電・放電を繰り返すことで、バッテリーが「記憶」してしまい、その「記憶」した容量しか使用できなくなる現象を指します。
例えば、50%の容量で充電を繰り返していると、バッテリーは100%の容量があると認識しなくなり、実際の50%の容量しか使用できなくなる可能性があります。
このメモリー効果により、バッテリーの寿命が短くなるだけでなく、走行距離も短縮されるリスクが高まります。
この効果を避けるための対策として、以下の点を守ることが重要です。
- 定期的にバッテリーをフル充電する。
- 長期間使用しない場合は、バッテリーを半分程度の容量で保存する。
- 低温や高温を避け、適切な温度での充電・放電を心掛ける。
これらの対策を実践することで、バッテリーの健康を維持し、長期間の使用を可能にすることができます。
電動自転車の維持費と経済性

電動自転車の維持費は、初めての購入者にとって気になるポイントの一つでしょう。
確かに、初期投資としての購入価格や、バッテリーの交換、アシスト機能のメンテナンスなど、普通の自転車と比較して特有のコストが発生するのは事実です。
例えば、バッテリーの寿命は平均で3〜5年とされ、その交換費用は20,000円から40,000円程度が一般的です。
自転車そのものの寿命は8〜10年くらいなので、1〜2回のバッテリー交換が必要です。
しかし、この維持費を車やバイクとの比較で見ると、電動自転車の経済性が際立ってきます。
ガソリン車や公共交通機関を利用する場合、月々のガソリン代や定期代、駐車料金などの出費が継続的に発生します。
これに対して、電動自転車の充電費用は1回あたり10円程度と非常に低く、年間を通しても大きな出費とは言えません。
このように考えると、電動自転車は日常の移動手段として、短期的な維持費の負担はあるものの、長期的には非常に経済的であると評価できます。
特に都市部での移動手段としては、交通渋滞や駐車場の問題も考慮すると、電動自転車のメリットは大きいと言えるでしょう。
普通の自転車との比較では「楽」であることが、なによりの優位点です。
電動自転車 中古はやめたほうがいい理由

電動自転車の市場は拡大を続けており、中古市場もその波に乗っています。
しかし、中古の電動自転車購入には潜むリスクが存在します。
中古で購入した電動自転車の約30%が1年以内に何らかのトラブルを経験しているというデータもあります。
主なリスクとしては、バッテリーの劣化や未知の事故歴、保証期間の短さや部品の取り扱いの困難さなどが考えられます。
一見、初期コストを抑えることができる中古の電動自転車も魅力的に思えますが、長期的な安全性や維持コストを考慮すると、新品の購入が結果的には経済的であるとも言えます。
電動自転車の選び方と購入のポイント
電動自転車の購入を検討する際、その多様なラインナップから最適な一台を選ぶのは容易ではありません。
以下に、購入の際に特に注意すべき5つのポイントを詳細に解説します。
- 使用目的の明確化:通勤・通学、買い物、レジャーなど、使用目的に応じたモデル選びが必要です。例えば、荷物を多く運ぶ場合はキャリアが強化されたモデルがおすすめです。
- 走行距離とバッテリー容量:日常の移動距離を基に、必要なバッテリー容量を見極めましょう。長距離を走行する場合、大容量のバッテリーを搭載したモデルが適しています。
- バッテリーの交換・メンテナンスの容易さ:バッテリーの取り外しや交換が簡単なモデルは、長期的な使用においてメンテナンスが楽です。
- アフターサービスと保証期間:長い保証期間や、メーカー・販売店の充実したアフターサービスは、安心して使用するための大きなポイントとなります。
- 予算とコストパフォーマンス:予算内で最も性能や機能が充実したモデルを選ぶことで、コストパフォーマンスの高い購入が可能です。
電動自転車は楽じゃない?:その誤解と真実とは?【まとめ】
この記事のまとめです。
- 電動自転車は普通の自転車よりも重い
- バッテリーの充電作業が煩わしい
- 都市部では電動自転車の盗難が増加している
- 小さなタイヤが段差の乗り越えに不利
- アシストを活用することで、ライダーは平均で約40%のエネルギー消費を削減
- ニッケル系バッテリーの「メモリー効果」により走行距離が短縮するリスク
- 電動自転車の維持費と経済性についての考慮
- アシスト機能の存在により、坂道や向かい風でもサポートが得られる
- スピードを出すならロードバイクの方が適している









