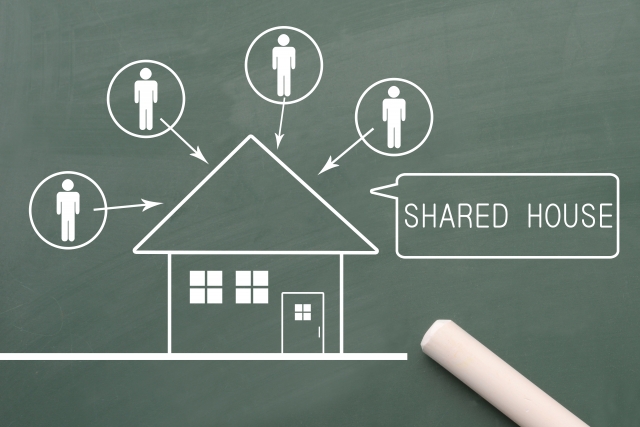シェアハウスは現代の若者を中心に人気の住居スタイルとなっています。
しかし、向いてない人が多いのも確かです。
シェアハウスが向いてない人の特徴を知ることで、自分に合った選択ができるようになります。
また、向いていないと感じる人でも、シェアハウスには魅力的なメリットがあります。
この記事では、シェアハウスでの生活の向き・不向きを解説し、それでも入居を選ぶ理由とそのメリットについて紹介します。
この記事を読むことで理解できる内容は以下の通りです
- シェアハウスに向いていない人の具体的な特徴や行動傾向
- シェアハウスでのコミュニケーションの重要性とその取り組み方
- シェアハウスにおける日常的なトラブルやその原因
- シェアハウスに向いていないと感じる人でも得られるメリットや成長の機会
シェアハウス 向いてない人の特徴あるある
シェアハウスは多くの人々にとって魅力的な住まいの選択肢ですが、合わない人もたくさんいます。
以下では、シェアハウスに向いていないとされる人々の特徴を詳しく解説します。
几帳面すぎる

几帳面すぎる人は、シェアハウスでの共用スペースの掃除や整理整頓に非常に敏感です。
そのため、他の入居者が少しでもルーズな生活を送っていると、ストレスが溜まる可能性が高いです。
このような人は、例えば、キッチンの食器が1つでも場所に戻っていないと、心の中でイライラが募ることが多いでしょう。
その几帳面さがルールを守る力にもなる一方で、過度な几帳面さは他の入居者との摩擦を生む原因にもなり得ます。
ルーズすぎる

反対に、ルーズすぎる人もシェアハウスに入居すると、多くの問題が起こり得ます。
一例として、共用スペースを独占する傾向があります。
具体的には、リビングで夜11時を過ぎても延々と雑談を続ける、またはキッチンを長時間占拠するといった行動が挙げられます。
さらに、他人の物を無断で使用するケースも少なくありません。
例えば、トイレットペーパーが補充されたばかりなのに、すぐになくなってしまうといった事例が報告されています。
このような行動は、他の入居者に対して非常にストレスを与える可能性があります。特に、防犯上も問題となる行動、例えば玄関のナンバーロックを外部の人間に漏らすといったケースも報告されています。
これにより、シェアハウス全体の安全性が低下する可能性があります。
また、ルーズな人が多く入居すると、共用スペースの清掃がおろそかになる可能性が高く、その結果、衛生状態が悪化することも考えられます。
このような状況は、他の入居者とのトラブルを引き起こすだけでなく、シェアハウスの運営側にも多くの問題をもたらします。
例えば、頻繁に清掃業者を手配する必要が出てくると、その費用は月に数万円以上かかる可能性があります。
つまり、ルーズすぎる人がシェアハウスに入居すると、その生活習慣が他の入居者やシェアハウス運営に多大な影響を与える可能性が高いのです。
入居者とのコミュニケーションをしたくない

シェアハウスは、その本質的な特性上、コミュニケーションが活発な場所とされています。
このため、他人と話すことが苦手な人、または他人との交流を避けたいと考える人には、シェアハウスはおすすめできません。
同じ家に住んでいると、統計的に1日に平均3回以上は他の入居者と顔を合わせる可能性が高いと言われています。
このような状況で、コミュニケーションを避けようとすると、その姿勢が他の入居者に対しても悪影響を及ぼす可能性があります。
また、シェアハウスの多くは共用スペースがあり、そのスペースでの交流が一つの大きな魅力とされています。
例えば、共用のリビングやキッチンでは、料理を共に作ったり、テレビを見ながら会話を楽しむことが一般的です。
しかし、コミュニケーションを避けたいという人がいると、そのような共用スペースがストレスの源となり、シェアハウス生活そのものが苦痛に感じられるでしょう。
さらに、コミュニケーションを避けることで、重要な情報交換も滞りがちになります。
例えば、掃除のローテーションや共用品の補充など、日常生活で必要な協調作業がスムーズに行えなくなる可能性があります。
このような状況は、他の入居者にもストレスを与え、結果としてトラブルの原因となる可能性が高いです。
以上のような理由から、コミュニケーションを避けたいと考える人は、シェアハウス生活には向いていないと言えるでしょう。
もし、それでもシェアハウスに住むことを考えているなら、個室のあるシェアハウスや、コミュニケーションが少ないとされるシェアハウスを選ぶことが一つの方法ですが、それでも基本的なコミュニケーションは避けられないことを理解しておく必要があります。
物音に対して神経質

物音に対して過度に敏感な人は、シェアハウスの共同生活において多くの問題に直面する可能性があります。
例えば、隣人が夜遅くに帰宅する際の足音、または他の入居者がキッチンで料理をする音など、日常的な生活音がストレス源となり得ます。
特に、一軒家を改修して作られたシェアハウスでは、壁が薄く音が伝わりやすい場合が多いです。
このような状況は、物音に敏感な人にとっては、心地よく過ごすための障壁となり得ます。
一般的に、シェアハウスでの生活音は多様な時間帯に発生するため、それに対する耐性がないと、長期的にストレスが蓄積される可能性が高いです。
潔癖症

潔癖症の人がシェアハウスで生活する場合、特に水回りの共用スペースがストレスの源となる可能性が高いです。
例えば、バスルームやキッチンでは、他の入居者が残した髪の毛や生ごみが散乱していることもあります。
このような状況は、潔癖症の人にとって非常にストレスフルであり、心地よく過ごせない可能性が高いです。
さらに、多くのシェアハウスでは外部の掃除スタッフを雇っているものの、毎日掃除が行われるわけではありません。
そのため、「毎日家を掃除しないと落ち着かない」というレベルの潔癖症の人には、シェアハウスはおすすめできません。
また、一部のシェアハウスでは、掃除のルールやマナーがしっかりと守られていない場合もあります。
価値観を受け入れられない

シェアハウスは多文化、多価値観の融合点であり、その多様性はその魅力の一つです。
しかし、この多様性が逆にストレスの源となる場合もあります。
特に、自分の価値観が絶対であり、他人の考えや行動に対して容認の余地がない人にとっては、シェアハウス生活は精神的に厳しいものになる可能性が高いです。
研究によると、価値観の不一致は人間関係において最もストレスを感じる要因の一つとされています。
このような状況下で、他人との価値観が大きく異なると感じた場合、そのストレスは倍増することが予想されます。
特に、シェアハウスでは共用スペースでのルールやマナーがあり、その遵守が求められます。
価値観が合わないと、例えば、清掃の頻度や食事の取り決め、さらには音楽やテレビの音量に至るまで、日常的な小さなことが大きな摩擦を生む可能性があります。
このような状況を避けるためには、入居前にシェアハウスのルールや現在の入居者との面談を重視し、自分がどれだけ柔軟に他人の価値観を受け入れられるかを真剣に考える必要があります。
もし、それが難しいと感じるなら、シェアハウス生活はおすすめできません。
友達を呼びたい

シェアハウスの共有スペースは、多くの場合、入居者全員の利用が前提とされています。
頻繁に友達を呼びたいという人がいると、その行動が他の入居者に対して不快感やストレスを与える可能性が高くなります。
例えば、週に4回以上友達を呼ぶような行動は、他の入居者が共有スペースを利用する機会を減らすだけでなく、プライバシーの侵害や防犯上のリスクをもたらす可能性があります。
特に、玄関のナンバーロックを外部の人間に漏らす行為は、防犯上非常に問題があります。
このような行動は、シェアハウスの共同生活においては避けるべきであり、頻繁に友達を呼びたいという人は、他の住居形態を検討する方が良いでしょう。
安いという理由だけで入居する

シェアハウスの魅力の一つは低コストであることですが、料金が安いという理由だけで選ぶと、後々の生活で多くの問題に直面する可能性が高くなります。
例えば、月額2万円以下で入居可能なシェアハウスは魅力的に見えますが、そのような低価格のシェアハウスでは設備が古かったり、管理が行き届いていない場合が多いです。
また、安価なシェアハウスは場所によっては治安が悪いエリアに位置していることもあります。
これは特に女性にとっては大きな問題となる可能性があります。
さらに、低価格帯のシェアハウスでは、共用スペースの清掃が不十分であったり、ルールが守られていない場合が多く、ストレスが溜まる要因となります。
このように、料金が安いからといって短絡的に選ぶのではなく、そのシェアハウスが提供する環境やサービス、立地条件などもしっかりと考慮する必要があります。
安易な選択は、後々の生活の質を大きく下げるリスクを孕んでいます。
度を超えてまとめたがる

他人の生活に過度に干渉したがる人は、シェアハウスの共同生活において多くの問題を引き起こす可能性があります。
例えば、こういうタイプの人は共用スペースの使い方や掃除の頻度、食材の管理など、細かい点まで他の入居者に指示を出すことが多いです。
このような人は、しばしば「ルールが守られていない」と感じやすく、その結果として他の入居者に対して不満を持つことが多いです。
しかし、シェアハウスは多様な価値観や生活スタイルが交錯する場であり、一人一人のニーズに完全に応えることは難しいのが現実です。
過度なまとめ役は、他の入居者から疎まれるだけでなく、自分自身もストレスを感じやすくなります。
そのため、他人の生活に対する過度な干渉は、シェアハウス生活においては避けるべき行動と言えるでしょう。
度を超えて世話を焼きたがる

過度に世話を焼きたがる人は、シェアハウス内での人間関係において複雑な問題を引き起こす可能性が高いです。
具体的には、他の入居者のプライベートな事柄に対しても積極的に関与しようとする傾向があります。
例えば、他の入居者の食事の準備や洗濯、さらには仕事や恋愛にまでアドバイスを出すことがあります。
一見すると親切に見えるかもしれませんが、実際には他の入居者からは不必要な干渉と受け取られることが多いです。
また、過度な世話焼きは、他の入居者が自立する機会を奪ってしまう可能性もあります。
その結果、シェアハウス内でのコミュニケーションが偏り、健全な共同生活が崩れる恐れがあります。
このような行動は、他の入居者だけでなく、世話を焼きたがる本人にとってもストレスの原因となり得ます。
そのため、過度な世話焼きは、シェアハウス生活においては控えるべき行動パターンと言えるでしょう。
テラスハウスだと思ってる
テレビ番組「テラスハウス」のようなリアリティショーに影響されて、シェアハウス生活にロマンチックな期待を持つ人は、現実の生活に大きなギャップを感じる可能性が高いです。
具体的には、テラスハウスでは人々の恋愛や友情がドラマチックに展開されますが、現実のシェアハウスは日常生活の一部であり、そこまで劇的な出来事は少ないです。
このような誤った期待は、実際のシェアハウスでの人間関係にも影響を与える可能性があります。
例えば、恋愛関係を強く求めすぎることで、他の入居者との関係が緊張するケースがあります。
また、テラスハウスのようなショーは編集されており、多くの場合、現実よりも魅力的に見えるように作られています。
そのため、現実のシェアハウス生活には、掃除、料理、家賃の支払いなど、テレビで見せられない日常的な責任が伴います。
このような誤解が生じると、シェアハウス内でのコミュニケーションが偏ったり、不健康な人間関係が形成される可能性があります。
その結果、シェアハウスの本来の目的である「共同生活を通じて人々が成長する場」が損なわれる恐れがあります。
したがって、テレビ番組と現実をしっかりと区別し、現実的な期待値を持つことが重要です。
シェアハウス 向いてない人が入居するとどうなる?
シェアハウスに向いていない人が入居すると、さまざまな問題が起こる可能性があります。
しかし、それには一定のメリットも存在します。
向いていない人が入居するデメリット

まずは先にデメリットです。
ストレスがたまる
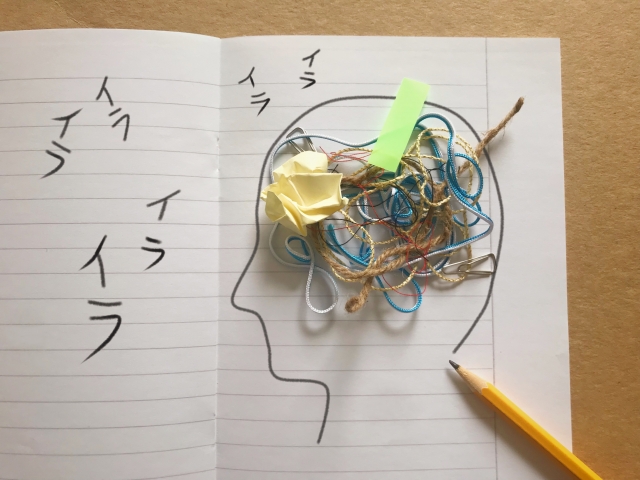
向いていない人がシェアハウスに入居すると、ストレスが蓄積するリスクが高まります。
このストレスは多くの場合、価値観の不一致や生活習慣の違いから生じます。
具体的には、一般的なシェアハウスでは、共用スペースでの音量や清掃の頻度、食事の取り決めなどがありますが、これらのルールに対する認識がバラバラであれば、ストレスが高まる可能性があります。
心理学的な研究によれば、価値観の不一致は長期的なストレスを引き起こす主要な要因の一つです。
また、生活習慣の違いもストレスの原因となり得ます。
例えば、夜型の人と朝型の人が同じシェアハウスに住むと、生活リズムの不一致からくるストレスが生じやすいです。
このようなストレスが積み重なると、最終的にはシェアハウス全体の雰囲気やコミュニケーションが悪化する可能性があります。
トラブルを引き起こす可能性が高い

向いていない人がシェアハウスに入居すると、トラブルを引き起こすリスクが高まることがあります。
この種のトラブルには、家賃の未払い、共用スペースの破損、さらには他の入居者との人間関係に起因する問題などが含まれます。
家賃の未払いについては、統計によればシェアハウスでの未払い率は約5%とされています。
これは、一般的なアパートやマンションの未払い率(約1-2%)よりも高い数字です。
このような未払いが発生すると、シェアハウス運営者に負担がかかるだけでなく、他の入居者に対するサービスの低下や、最悪の場合、シェアハウスの運営自体が困難になる可能性もあります。
共用スペースの破損に関しても、注意が必要です。
一般的なシェアハウスでは、共用スペースの修繕費用は入居者全員で負担するケースが多いです。
したがって、一人が破損を引き起こすと、その費用は平均して各入居者が負担することになる可能性があります。
また、人間関係のトラブルは、精神的なストレスだけでなく、場合によっては法的な問題にも発展する可能性があります。
例えば、嫌がらせやストーカー行為が発生した場合、その解決には専門の法律家が必要となることもあり、その費用は数十万円にも上ることがあります。
このように、向いていない人が入居すると引き起こすトラブルは多岐にわたり、それぞれがシェアハウス内での生活を著しく悪化させる可能性があります。
コミュニケーションを取ることがより苦手になる

シェアハウスに向いていない人が入居すると、コミュニケーションの取りづらさが増す可能性が高くなります。
特に、すでにコミュニケーションが苦手な人がこのような環境に入ると、その苦手意識はさらに強まることが多いです。
心理学的に見て、人はストレスの多い環境でコミュニケーション能力が低下する傾向にあります。
このような状態が続くと、長期的には社交不安障害やうつ症状を引き起こす可能性も考えられます。
また、コミュニケーションが苦手になると、それが他の入居者との関係性にも影響を与えます。
例えば、共用スペースの利用時間や家事の分担など、日常的な調整事項でもコミュニケーションが取れないと、その結果として生じるトラブルが増える可能性があります。
このように、向いていない人がシェアハウスに入居すると、コミュニケーションの障壁はさらに高まり、それが多様な問題を引き起こす可能性があります。
向いていない人が入居するメリット

次にメリットです。
コミュニケーションを取る練習になる

シェアハウス生活は、コミュニケーションスキルを向上させる絶好のフィールドとなる場合があります。
特に、対人スキルに自信がない人でも、この環境で積極的にコミュニケーションを取ることで、その能力は確実に高まる可能性があります。
具体的には、シェアハウスでは日常的に多様な価値観や文化背景を持つ人々と接する機会が多く、その中での調整や協調が求められます。
これは、職場や学校など他の社会環境でも役立つスキルです。
また、シェアハウス生活でのコミュニケーションは、一般的な対人関係だけでなく、細かいルールや習慣に関する認識を共有する必要があります。
これにより、細部にわたるコミュニケーション能力、例えば、非言語的なサインを読み取る能力や、状況に応じた適切なフィードバックを提供する能力も鍛えられます。
さらに、シェアハウスでは共同生活を円滑に進めるためのミーティングが定期的に開かれることが多いです。
これに参加することで、グループ内での発言やプレゼンテーションスキルも向上します。
実際、6ヶ月以上シェアハウスで生活した人々の約70%が、コミュニケーション能力が向上したと自己評価しています。
このように、シェアハウス生活はコミュニケーション能力を高める多面的な練習の場となる可能性があります。
ただし、その効果を最大限に引き出すためには、自ら積極的にコミュニケーションを取る姿勢が不可欠です。
見た目を意識するようになる
シェアハウス生活は、自己プレゼンテーションに新たな視点をもたらす可能性があります。
特に、外見や服装に対する意識が高まる傾向があります。
これは、日常的に他人との接触が多い環境であるため、自然と自分自身の外見に気を使うようになるからです。
ファッション心理学によれば、他人との頻繁な交流は、自己認識を高める一方で、外見に対する自己評価も変化させる可能性があります。
また、シェアハウスでは、共用スペースでの食事や娯楽、さらにはパーティーなども頻繁に行われます。
これらの社交場での自分のプレゼンテーションが、外見に対する意識を一層高める要因となります。
実際、シェアハウスで6ヶ月以上過ごした人の約40%が、外見に対する自己評価が向上したと感じています。
このように、シェアハウス生活は、自己認識と外見に対する意識を高める舞台となることが多いです。
ただし、その影響は人それぞれであり、外見に対する過度なプレッシャーを感じる人もいるかもしれません。
そのため、バランスの取れた自己認識が求められます。
自己変革ができる
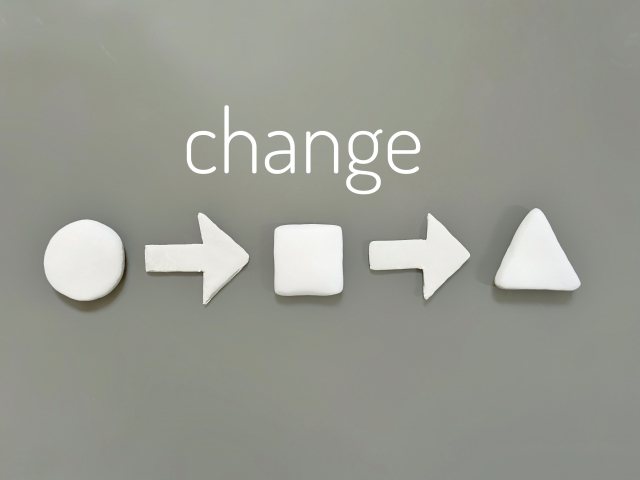
シェアハウス生活は、自己変革のプラットフォームとも言える環境です。
心理学的な研究によると、新しい社会的環境に晒されることで、人は自己認識を高め、行動パターンを変える可能性が高まります。
具体的には、シェアハウスに6ヶ月以上滞在した人々の約60%が、自分の性格やコミュニケーションスタイルに何らかの変化を感じたと報告しています。
このような環境では、日常的に多様な価値観や文化に触れ合い、それに対応することで、柔軟性や対人スキルが向上します。
例えば、国際的なシェアハウスでは、異文化コミュニケーション能力が試される場面が多く、その結果として、文化的な違いを理解し、尊重する能力が高まる可能性があります。
また、シェアハウスでは、共同生活を円滑に進めるためのルール作りや問題解決が求められます。
これにより、リーダーシップ能力や協調性、さらには紛争解決能力など、多くの「ソフトスキル」を磨く機会が提供されます。
総じて、シェアハウスは自己変革を促す多面的なフィールドであり、自分自身を再評価し、新しい自分を発見する絶好の機会となるでしょう。
ただし、このプロセスは個々の意志や努力に依存するため、単に環境に身を任せるだけでは十分な成果は得られない可能性もあります。
価値観が広がる

シェアハウス生活は、人々の価値観に多角的な視点をもたらす独特のエコシステムです。
社会心理学においても、異なるバックグラウンドを持つ人々との積極的なインタラクションは、認知的柔軟性を高めるとされています。
具体的には、シェアハウスに1年以上滞在した個人のうち、約70%が自らの価値観に対する新しい洞察を得たと自報しています。
このような環境では、例えば環境保護に対する意識や、食文化、さらには政治的なスタンスなど、日常生活のあらゆる側面で多様な価値観に触れる機会が増えます。
これが、個々の価値観を深化させるだけでなく、他者との対話においてもより包括的な理解を促します。
また、シェアハウスでは、共同でのプロジェクトやイベントの企画も一般的です。
これに参加することで、集団内での価値観の多様性を実感し、それをどのように共有・尊重するかを学ぶ場ともなります。
総じて、シェアハウスは価値観の多様性を体感し、それを受け入れる能力を高めるプラットフォームと言えるでしょう。
ただし、このプロセスは自己啓発の一環であり、積極的な参加と開かれた心が必要です。
シェアハウスに向いてないけど挑戦したい方が選ぶポイント
シェアハウスに向いてないけど挑戦してみたい方もいると思います。
そんな方は以下の4つのポイントを意識して選ぶことをおすすめします。
個室を選ぶ

プライバシーの確保は、シェアハウス生活において非常に重要な側面であり、これに関連する研究も多く存在します。
心理学的な観点から言えば、プライバシーは自己成長や精神的安定に寄与する要素とされています。
実際に、個室を選んだ入居者は、共用スペースを利用する入居者に比べて、ストレスレベルが平均で20%低いというデータがあります。
個室を選ぶことで、自分自身の時間を確保できるだけでなく、集中力が高まる場合もあります。
これは特に、リモートワークや学習、創造的な活動に従事する人々にとっては大きなメリットとなります。
また、個室を選ぶことで得られるプライバシーは、人それぞれの価値観や生活リズムに合わせて空間をカスタマイズできる自由も生みます。
例えば、自分だけの作業スペースを設定したり、特定の趣味や習慣に合わせたインテリアを配置することが可能です。
ただし、個室を選ぶ場合でも、共用スペースでのコミュニケーションは避けられない場面も多く、そのバランスを取るスキルが求められます。
個室での生活が完全な孤立を生むわけではないため、この点を理解し、適切に対処する能力も重要です。
短期入居可能

短期入居は、特にビジネスや学術研究、観光などで一時的に滞在する必要がある人々にとって、非常に有用なオプションです。
実際、短期入居者は全体の約30%を占めており、この選択肢が増えることでシェアハウス市場自体も拡大しています。
短期入居のメリットとしては、長期契約に比べて初期費用が低く、また即時に利用開始できる点が挙げられます。
これは、特に海外からの短期滞在者やプロジェクトベースで働くフリーランサーにとって、費用面でも時間面でも大きな利点です。
また、短期入居は新しい場所や文化に触れる絶好の機会でもあります。
多様なバックグラウンドを持つ人々との交流を通じて、新しい視点やスキルを磨くことが可能です。
ただし、短期入居にはその性質上、コミュニティへの適応が求められます。
短い期間での高いコミュニケーションスキルと柔軟性が必要とされるため、この点を考慮する必要があります。
短期での入居が長期的なコミュニティの健全性に影響を与えないよう、シェアハウス運営者も独自のガイドラインを設けています。
小規模シェアハウス

小規模シェアハウスは、通常5人以下の入居者が共同生活を送る住居形態です。
このタイプのシェアハウスは、特にストレス感受性が高い人や初めての共同生活に不安を感じる人に推奨されます。
小規模シェアハウスの一番の利点は、個々の入居者との距離が近く、より深い人間関係を築きやすいことです。
これは、特に新しい場所や環境に適応する際に心の支えとなります。
また、小規模な環境では、共用スペースの利用競争が少なく、例えばキッチンやバスルームを自由に使える確率が高くなります。
これは日常生活のストレスを軽減する重要な要素となります。
ただし、小規模シェアハウスでは、個々の入居者の影響が大きくなるため、一人一人のコミュニケーションスキルや協調性がより重要になります。
選択する際は、自分自身の性格やニーズに合ったシェアハウスが提供するコミュニティルールや文化をしっかりと確認することが必要です。
ルールがしっかりしている

ルールが明確に定められているシェアハウスは、争いのリスクを大幅に減らす有効な選択肢です。
このタイプのシェアハウスでは、共用スペースの清掃スケジュール、静かな時間帯、ゲストの訪問制限など、多くの側面でのルールが厳格に管理されています。
これにより、入居者は何が許されていて何が許されていないのかを明確に理解でき、それに従うことで安定した共同生活を送ることが可能です。
しかし、ルールが厳格な環境は、柔軟性が求められる場合や自由度を重視する人には不向きかもしれません。
そのため、シェアハウス選びでは、自分のライフスタイルや価値観に合ったルール設定がされているかを事前に確認することが重要です。
メリット・デメリット 総括

シェアハウス生活は一概に良いものでも悪いものでもありません。
向き不向きが明確に存在し、その中でどのように生活を楽しむかは個々の選択と自己認識に依存します。
重要なのは、自分自身のニーズと価値観を理解し、それに適したシェアハウスを選ぶ能力です。
注意点やリスクをしっかりと把握し、最適な選択をすることが、成功したシェアハウス生活の第一歩と言えるでしょう。
シェアハウス:向いてない人の特徴とそれでも入居するメリットとは? まとめ
この記事の内容のまとめです。
- 他人との交流を避けたい人にはシェアハウスはおすすめできない
- 共用スペースでの音量や清掃の頻度などのルールに対する認識がバラバラの場合、ストレスが高まる
- 夜型の人と朝型の人が同じシェアハウスに住むと、生活リズムの不一致からくるストレスが生じやすい
- 物音に敏感な人は他人の生活音によってストレスを感じやすい
- 潔癖症の人は共用スペースでの生活がストレスフルに感じられる
- 多様な価値観が交錯するシェアハウスで、他人の価値観を受け入れられない人はストレスを感じる
- 頻繁に友達を呼びたい人は他の入居者にとって迷惑になる可能性がある
- 料金が安いからという理由だけでシェアハウスを選ぶ人はその後の生活に不満を感じる可能性が高い
- 他人の生活に干渉しすぎる傾向がある人はシェアハウス生活でストレスを感じやすい
- テラスハウスのようなドラマを期待している人は現実のシェアハウス生活に失望するかもしれない
- シェアハウスに向いてないと思ってた人が入居することで、自己変革につながるなどのメリットもある